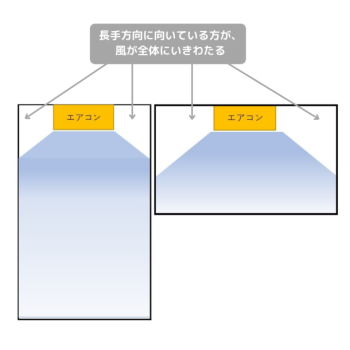- 2022.07.13
- 家に関するお金の話
他人の家と価格を比較してもあまり意味がないかも…
家を建てる際に、過去に家を建てた人の金額を参考にする方は多いと思います。 『○○さんちは2500万円で、◇◇さんちは3000万かぁ~。じゃあうちは2700万円くらいを目安にしようかな~』なんて方もいるのでは? しかし、それってあんまり意味がないかもしれません。 他人の家と価格を比較してもあまり意味がないかも… 例えば、○○さんちを見に行って、 『家族構成も同じで生活スタイルも似ているし、○○さんちの家の間取りが気に入ったからまったく同じ場所に全く同じ家を建てたい!』 …のように、まったく同じ家を建てる場合には価格の比較は意味を持ちます。◆◆電気のほうが▼▼電気よりも同じエアコンが安い!と比較するのと同じですからね。 しかし、実際には、友人知人の家をある程度参考にしたとしても、全く同じ家を建てることってほとんどないですよね? 家は、 ・家族構成 ・趣味や好み ・重要視するポイント ・将来の展望 ・立地、土地 などによって作り方が大きく変わります。家族ごとの要望を盛り込んだ家にすることで、長く快適に安心して暮らすことができるんですね。 家は誰かの家と同じものを作るのではなく、自分達の生活スタイルに合ったものにすることが重要です。 そして、家の価格は『この大きさだから○○万円です』という風に決まっているわけではなく、 ・広さ ・間取り ・素材 ・採用するもののグレード ・土地購入の有無 ・建てる時期の物価 などによって金額が大きく変わります。さらに金銭面のことで言うと ・頭金をどれだけ貯めていたか? ・親からの援助があったのか? などによっても、負担額は変わってきます。 そのため、『○○さんの家が△△万円』というのは、家の金額を決めることの参考にならないんですね。 単純な価格比較をおすすめしないのはこういった理由があるからなんです。 ローンの月々返済は参考になる? 家の金額は作りによって違うため、比較にはあまり意味がありません。では『住宅ローンの月々の支払額』はどうでしょう? 例えば同じ共働き夫婦で、家族構成や世帯年収が似ている家庭の場合、月々の支払額がいくらで、その金額なら生活に余裕があるのか?それともローンの支払いで生活が苦しいのか?といったある程度の目安にはなるかもしれません。 ただし、生活スタイルによって月々の生活費も異なりますし、毎月の出費というのもまた家庭によって全く違ってきます。その他、貯蓄をいくらしいるのか???将来的に家族構成が変わる可能性はないか?などでもローンの支払い負担はかわりますよね? そのため、ローンの月々返済額もあくまで参考程度にしかならないと考えた方がよいでしょう。 他人との比較よりも、自分たちに合った予算・家づくりを ここまでご紹介した通り、他人の家との価格比較はあまり意味がありません。 もっと言ってしまえば、5000万円の家を建てても余裕の人もいれば、2000万円の家でもローン返済がギリギリ…。という人もいらっしゃいます。 他の人と比べるのではなく、自分達にはどれだけの予算がふさわしいのか?いくらくらいまでなら無理なく支払えるのか?をきちんと計画する方が安心です。 そしてその予算の中で、いかに自分たちが生活しやすい家を作ることができるかが重要です。 予算も家の間取りも、十数年先を見据えた理想のプランを考えていきましょう。迷ったら私達石丸ハウスセンターにお気軽にご相談くださいね♪ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 福井県坂井市で家を建てるなら、三国町の工務店『石丸ハウスセンター』へ。 注文住宅・新築・リフォームはもちろん、住まいのお困りごともお気軽にご相談下さい。 【ずっと側にいる、という安心。】 徹底した地域密着主義で私たちがお届けするのは、「安心」という価値です。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
more