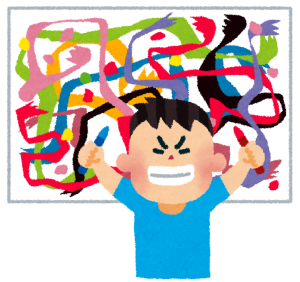- 2022.06.13
- インテリア・設備
室内用の壁材にもいろんな種類があります。
家の外観に大きく影響を与えるのは『外壁材』ですが、では室内はどうでしょうか? 室内にも壁があり、壁に使う材料で雰囲気はがらりと変わります。 そこで今日は【室内用の壁材】についてご紹介します。 室内用の壁材にもいろんな種類があります。 では、室内に使う壁材には、どんな種類があるのでしょうか? 大きく分けると… ・壁紙(クロス) ・塗り壁 ・タイル ・木材 の4つが主に内装に使われる壁材になります。これらを組み合わせながら内壁を作っていくんですね。 続いてそれぞれの特徴を見ていきましょう。 壁紙(クロス) 内装用の壁材で一番良く使われるのが壁紙です。クロスと呼ぶこともあります。 ビニールなどでできた薄いシートを壁に貼り付けていく工法で、施工が比較的簡単なため、費用を抑えることができます。 様々な色柄から選ぶことができるので、うまく取り入れることで自分の好きなイメージを作り上げることができます。 また、消臭効果や防汚効果、調湿効果のある壁紙など、機能性を持たせた壁紙もあり、使用用途に合わせて選ぶことができます。 塗り壁 塗り壁は日本で古くから用いられてきた内装材の一つ。 土や草、水などの自然素材をこねたものを、左官職人さんが丁寧に塗り付けていくことで完成し、クロスには決して出すことのできない質感が魅力です。 例えば、【土壁】は古い和室などで見たことがある方も多いのではないでしょうか?その名の通り土を塗り付けて壁を作る方法で、ざらっとした表面が特徴的です。 【珪藻土】の塗り壁も、土壁と同じようにざらっとしていて凸凹がある独特の質感で、調湿、消臭効果があるのが特徴です。 もう一つ有名なのが【漆喰】です。漆喰は消石灰をつかった白い壁材で、外壁にも使われる素材のため耐久性があり、つるっとした見た目が特徴です。 塗り壁は素材の質感を活かした雰囲気の出る壁材ですが、その性質上ヒビが入ったり割れたりすることがあります。 タイル 大小さまざまな形のタイルを貼って仕上げます。 タイルにはカラフルなものがたくさんありますし、つるつるしたものやさらっとしたもの、ざらざらしたものなど質感もいろいろなため、組み合わせ次第でいろいろな雰囲気を楽しむことができます。タイル以外にレンガを使ったりもします。 タイルは水や汚れに強いため、キッチンや洗面台などの水回りに使われることも多いです。 万が一割れてしまっても、割れた部分だけを貼り変えることもできるため、塗り壁よりもメンテナンスは簡単です。 木材 木材は家の様々な場所に用いられる部材で、もちろん壁にも使うことができます。 壁に使う木材としては『無垢材』と『合板』がありますが、より木の雰囲気を楽しみたいのであれば『無垢材』を選ぶと良いでしょう。 部屋全体に使うとログハウスのようになってしまうので、壁全面よりは、テレビボードの裏などの一面にアクセントとして使うのがおススメです。 その他の壁材 以上、4つの良く使われる壁材を見てきましたが、他にもちょっと変わった壁材があるのでご紹介します。 まずは【コンクリート】。 構造に使ったコンクリートをそのまま室内の壁として見せるもので、その無機質な質感に人気があり、デザイナーズマンションなどでも取り入れられます。 反面、コンクリートの家は断熱に工夫が必要になるなど、施工が大変な部分もあります。 専用のペンキを塗る【ペイント仕上げ】という方法もあります。 あまりなじみがないように感じますが、マンションのリノベーションなどにはよく使われる工法ですし、海外のドラマなどを見ていると、自分たちで壁に色塗りをしているシーンがあったりと、意外とポピュラーな方法です。 施工費が安く、自分でも比較的簡単に塗り直しができる反面、剥がれや汚れが起きやすく、数年に一回は塗り直しが必要になるため、こまめに自分で手入れができる方にお勧めしたい方法です。 色柄物はワンポイントで 部屋の壁全体に色柄物の壁紙を使ったりすると、落ち着きのない部屋になってしまい、飽きが来やすくなってしまいます。 長時間過ごすリビングや寝室の場合、色柄物の壁紙やタイル、木材などは壁の一面のみとするなど、アクセント的に使うのがおススメです。 トイレやクローゼット、書斎等個室の中は、前面柄や素材を使うなど少し大胆にしてみてもいいかもしれませんね。 お洒落にしたいけど費用が気になるなら 塗り壁やタイル、木材などを壁面に取り入れることで、オシャレで個性的な雰囲気を作ることができます。 しかし、ネックなのが費用です。塗り壁などは壁紙と比べるとどうしても金額が高くなりがちで、費用的にあきらめてしまう人もいらっしゃいます。 そんな時におススメなのが、各素材の柄がプリントされた壁紙です。 塗り壁風、タイル風、木材風、コンクリート風など、様々な柄の壁紙があり、ただプリントしてあるだけでなく素材の凸凹感まで表現しているものもあり、ぱっと見は本物と見間違えてしまうものもあります。 これなら価格を抑えて部屋にアクセントを取り入れることができますね。 しかし、やはり本物と比べると若干見劣りするため、リビングなどのメインルームには本物の素材を、トイレや寝室などには柄の壁紙を使うのがおススメです。 メリハリをつけることで費用を抑えつつ、お洒落な家づくりを目指しましょう。 まとめ 今回は内装に使う壁材についてご紹介しました。 部屋の壁は毎日必ず目に入るもの。壁の素材の雰囲気で過ごす人の気分が変わるのは間違いありません。また、壁は家の中で面積が一番広い部分になるため、壁材一つでも機能性や暮らしやすさに影響します。 ぜひ今回の内容を参考に、あなたのイメージに合った壁材を使って理想の内装を目指してくださいね。 ☟関連ブログはコチラ☟ 『クロスなどの色選びの注意点』 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 福井県坂井市で家を建てるなら、三国町の工務店『石丸ハウスセンター』へ。 注文住宅・新築・リフォームはもちろん、住まいのお困りごともお気軽にご相談下さい。 【ずっと側にいる、という安心。】 徹底した地域密着主義で私たちがお届けするのは、「安心」という価値です。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
more